
2025.12.26
音楽創造ワークショップ
注目キーワード
お気に入り公演とは?
チケットの販売状況は日々変化しているため、お早めのご購入をお願いします。
月別
公演ジャンル
会場
指揮者
その他条件
超大作の迷宮をともに探検する旅 マーラーの交響曲第3番の背景と特徴を探る
会場には6つのテーブル。それぞれの上には思わせぶりなモノがポツンと置かれていた。
かつて「最長の交響曲」としてギネスブックにも掲載されたこの曲。本番を聴いた時、ああ、こうだった!と思い出せるような道しるべはあるのだろうか?
1 激動の時代に生きた作曲家の道行き
常に「自分とは何か?」と悩み、振り返りつつ生きたマーラーは、音楽の中にその迷える自分自身を投影している。そんなマーラーの作曲家としての歩みの話からセッションは始まる。これまでのワークショップと比べると、いわゆる「座学」、すなわち作品の背景についてのレクチャーに、マイケル・スペンサー(日本フィルハーモニー交響楽団 コミュニケーション・ディレクター 以下、マイク)は長い時間を割いた。
19世紀末。600年続いたハプスブルク体制の崩壊から、間も無く訪れる第1次世界大戦へとつながる、あらゆるものが激変したヨーロッパ社会に翻弄されたマーラー。ユダヤ教からローマカトリックへの改宗を余儀なくされつつ、彼の中には、奔放に流浪し来世の復活を信じるユダヤの血が残されてもいた。そして哲学者、文学者たちとの交流を通じ、中世の物語「魔法の角笛」と出会う。職業指揮者という職種が確立した時代にあってその最先端に立つ一方、休日には自然を愛でた。「夏の作曲小屋」の窓から見える風景もまた、彼の作品の背景音だ。そしてあえて古典音楽の構築性を捨て、マーラーは自分の体験、思想、それに彼が見た風景や聴こえた音を題材に、音のエッセイを描く。自分の主観をいかに誇張して描いたか。ゴッホ、カンディンスキーやココシュカの絵も見ながら、「表現主義」について考えてみる。
この長大な交響曲の本質を多少なりとも実感するためには、今回、時代とマーラーの人となりの背景を理解しておくことがどうしても必要だった。マイクは今回のワークショップをデザインするうえでそう考えたという。
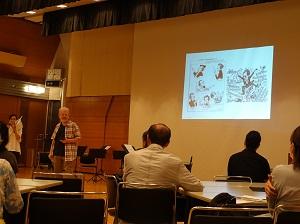
2 各楽章の道しるべを辿る
休憩を挟み、後半では実際に各楽章の音楽的特徴について、日本フィルのメンバーによる室内楽の実演や映像も交えて体験する。
第2楽章:第2のテーブルにはダンスシューズ。弦楽四重奏の実演とともに、参加者はメヌエットを踊った。バロック時代から続く舞曲の引用の伝統に倣いつつさらにマーラーは進化させた。そして花が咲き乱れる風景。マーラーの「音のエッセイ」はガラッとテーマを変えて次々と、そして多層的に描かれていく。
第3楽章:第3のテーブルには鳥の絵。夏の到来とともに、カッコー、ナイチンゲールはじめいろいろな動物の鳴き声がこの楽章で登場する。そして突然、シーンが変わる。バンダ(舞台裏での別働隊の演奏)のフリューゲルホルンを実際に首席トランペット奏者オッタビアーノ・クリストーフォリが吹く。


第4楽章:第4のテーブルには弦楽器の弓。チェロが2音のハーモニーを弱音のトレモロで保ち続ける。マーラーが多用した表現手法という。その背景音のなかに、夜の動物の声が聴こえてくる。そしてニーチェの「ツァラトゥストラ」から夜の歌。暗くもの悲しく憂鬱でありながら、人の思索が深められるのもまた夜。やがて夜明けは来る。その日のための前触れだ。
第5楽章:第5のテーブルにはベル。天使たちの語りとその背景音としての「鐘の音」が女声合唱と児童合唱で描かれる。室内楽の実演に重ねて、参加者たちがこの合唱を実際に歌ってみた。
第6楽章:第6のテーブルには1本の糸。この楽章で奏者にマーラーが求めた表現の象徴として、マイクは張り詰めた糸を用いた。たった一つの緊張の高まりを終始保ち続ける。その感情の陰影を描くために、弦のポジション、奏法、ビブラートの幅の指定に至る細かい表現の指定がある。弦楽五重奏による実演でそれを聴いた。
第1楽章:「何処を通ってきたかを知るまでは、何処へ行こうとしているかを知ることはできない。」
マイクは、アメリカの人権運動家・詩人・音楽家マヤ・アンジェロウの言葉を引用して、第3交響曲全体の構造、あるいはその構造を考えるに至ったマーラーの思いを理解するための助けとしている。最後までいきつかないと、どう始めるかを思い付けなかったのではないか?と。
紆余曲折し、アイデアも頻繁に変わった第2楽章から終楽章だが、全体を貫くテーマは、「永遠の、普遍の愛」へと向かうこの星の道行き。地球の誕生から再生までを追う物語、とマイクはいう。
では最後にその冒頭楽章としてマーラーは何を置いたか。「パンが目覚める。夏が行進してくる。」この、他の楽章と比べてもとりわけ抽象的で難解な言葉が手がかりだ。ギリシャ神話のパン(牧羊神)は、混乱、カオスの象徴と言われていて、「パニック」の語源でもある。その混乱をマーラーは葬送行進曲で表わす。ダン・ダダダ・ダーンという特徴的なリズムを、トロンボーンの実演に重ね、参加者は実際に手で叩いてみた。
冒頭のホルンの合奏はブラームスの「大学祝典序曲」と共通して、当時の学生たちの民主化運動の象徴として歌われた学生歌が題材だ。そうした社会問題も込めつつ、そのカオスのなかから地球が生まれ、自然界、思索する人、天使たち、それぞれからの語りかけを経て徐々に世界が和解と新しい秩序へと向かい生まれ変わっていく。壮大なこの曲の道行きについて、私たちは最後の理解へと至る。

3 私たちは音楽を通じてどう生きるか?
今回のワークショップでは、グループワークによる音楽創作の体験がなかった分、セッションの最後には、今回実演に参加した楽員との質疑応答の時間が設けられた。
「長大なこの曲を眠らずに聴くにはどうしたら?」という、ある切実な質問が、実は「演奏する/聴く」という行為の本質に迫るドアを開いたのがとても印象的だ。聴いていく中に、常に新しい発見を見出すこと。それが「眠らずに演奏会を聴く」ためのキーであり、実は奏者も常に新しい発見をし、しかもそれを元に奏者同士、奏者と指揮者との間で交信を交わしていく。それがオーケストラプレイヤーとしての喜びであり、務めでもある。ロンドン交響楽団のヴァイオリン奏者でもあったマイクを含めた、音楽家たちの率直な声が聞けた。さらにこんな話へと進む。
「音楽家のもう一つの大切な仕事は、聴衆との繋がり、関わりを持つこと。一人の指揮者との関係は一時的なものだが、聴衆との関係は永続的なものなのだから。」そのマイクを継いで、ヴィオラ奏者の中川裕美子は自分自身の問題としてこう語る。「演奏家と聴衆がその日の音楽を通じて感じた幸せをそれぞれの家に持って帰り、帰った場所へも波紋を起こし、大きく言えばそれは世界の平和にもつながっていく。オーケストラにはそんな使命があり、音楽にはそれを叶える力がある。何を伝え、何を持って帰ってもらえるか?それが社会にどういう影響をもたらすか?そういうことをいかに高レベルなものまで持っていけるか?」と。
楽曲について知りたいことは、今ならネットで簡単に情報を集められるだろうし、動画配信で音源も聴ける。しかしながら、「オケのテイキは、おもしろい」の醍醐味はなんと言っても実際に参加者が体を動かして作曲家のアイデアや想いを追体験できることにある。そして今回のように、奏者の生の声を聴ける貴重な場でもあり、聴衆と奏者の距離が一気に縮まったひとときでもあった。(実はワークショップ後の反省会では、楽員自身、さらにマイク自身、この曲についての新しい発見があったという。)
さらにもう一つ付け加えれば、名手オッタビアーノの見事なフリューゲルホルンのソロ、さらに終楽章の弦楽合奏の、本当に心震えるような瞬間が眼前にあった。こんな素敵なワークショップが他にあるだろうか?
山口 敦(テキスト・写真)










<オケのテイキはおもしろい 実施概要>
日 程:2023年9月18日(月・祝)14時~16時30分
会 場:千代田区いきいきプラザ一番町 カスケードホール
ワークショップデザイン:マイケル・スペンサー(日本フィル コミュニケーション・ディレクター)
通 訳:堀 美夏子
ファシリテーター
日本フィルハーモニー交響楽団
ヴァイオリン 伊藤 太郎、竹歳 夏鈴、佐藤 駿一郎 ヴィオラ 中川 裕美子 チェロ 大澤 哲弥
ファゴット 中川 日出鷹
トランペット オッタビアーノ・クリストーフォリ トロンボーン 伊波 睦
スタッフ
音 響:庄子 渉、石川 清隆
制 作:日本フィルハーモニー交響楽団